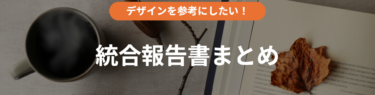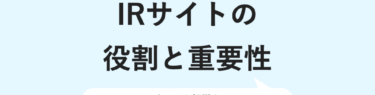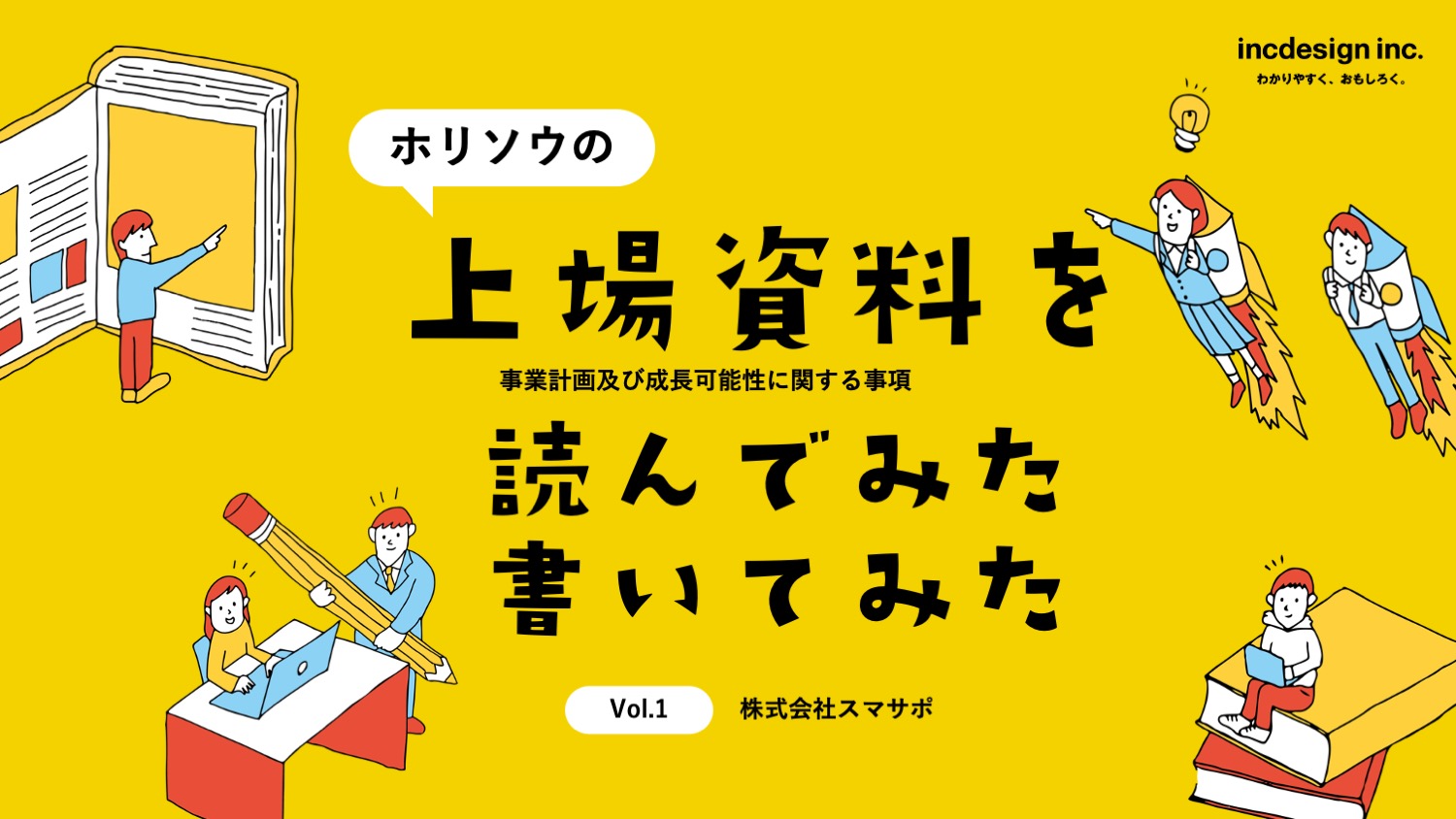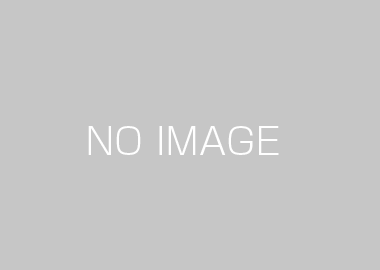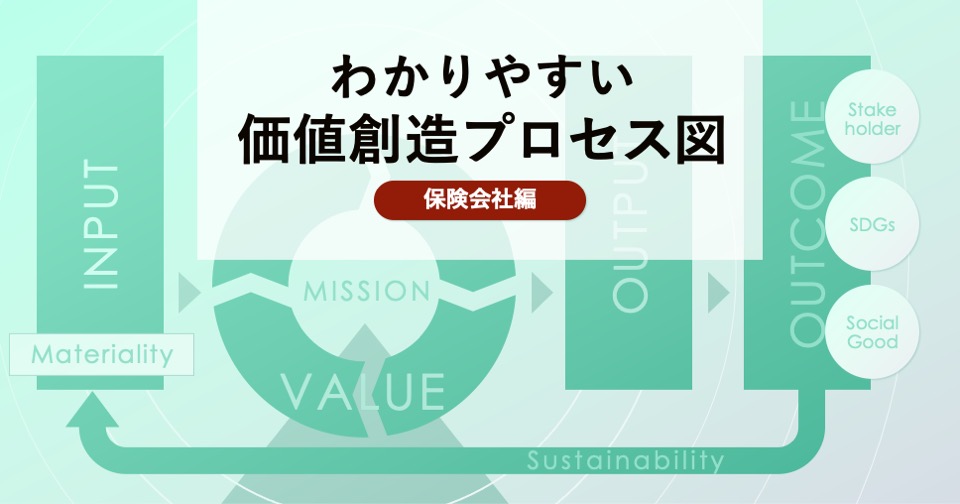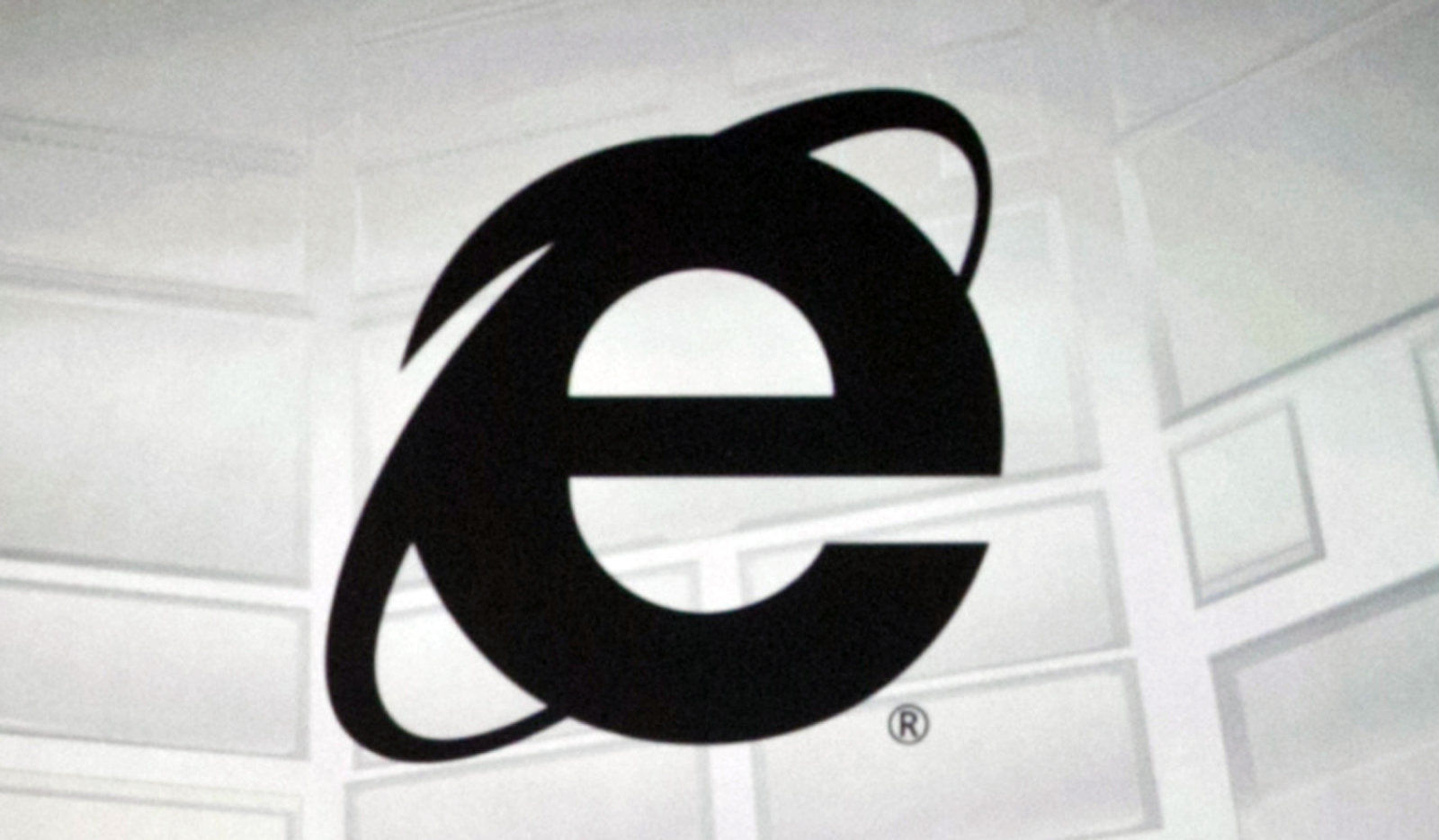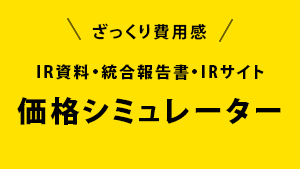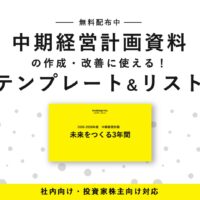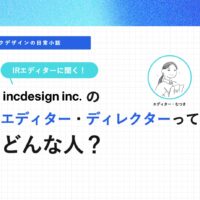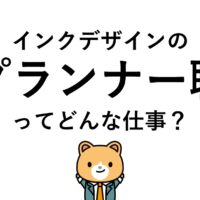こんにちは。入社3年目のHARUKAです!
先日公開した「新人でもわかる!IR基本用語をやさしく解説」は各方面から好評いただいています!
今回は第2弾として、「ビジネス用語」を解説します!
IT関係やスタートアップ関連では、専門用語や略語など多く、わからないことも多いです。
今回はそんなビジネスで使用する用語をまとめてみました!
かなりボリュームが多くなってしまいましたが、IR資料内での使い方も記載していますので参考にしてください!
1. 全般
スタートアップ(Startup)
定義・意味:
革新的な製品や技術・アイデアで新市場を切り開き、投資家から資金調達を受けつつ上場やM&Aを目指して急成長を狙うベンチャー企業のこと。
一般的な中小企業の創業とは異なり、短期間でのスケール(成長拡大)を前提としています。
IR資料での使われ方:
IRや投資家向け資料では、自社を説明する際に「当社は〇〇分野のスタートアップです」のように使われます。スタートアップであることは、成長余地の大きさやイノベーション性を示唆し、投資家に高成長期待を持ってもらうためによく強調されます。
ユニコーン企業(Unicorn Company)
定義・意味:
評価額(企業価値)が10億ドル以上で、創業10年以内の未上場スタートアップ企業のことです。
非常に希少な存在で、「ユニコーン(幻の一角獣)」になぞらえて呼ばれます。
なお、評価額100億ドル以上は「デカコーン」、1000億ドル以上は「ヘクトコーン」と呼ばれます。
デカい!??
IR資料での使われ方:
ユニコーン企業は投資家にとって大きな成功例の代名詞です。IR文脈では「将来的にユニコーン企業を目指す」「当社の評価額はユニコーン水準に達した」といった表現で使われます。企業規模や将来性を示すインパクトのある言葉として注目されます。
エグジット(Exit)
定義・意味:
創業者や投資家が出資したスタートアップから投資回収をすることを指し、具体的には株式売却やIPO(新規株式公開)によって利益を得ることです。スタートアップにおける「ゴール」の一つで、「出口戦略」とも言われます。
IR資料での使われ方:
「エグジット」はVC(ベンチャーキャピタル)やエンジェル投資家が特に関心を持つポイントです。IRでは「IPOをエグジット戦略として視野に入れている」「将来的なエグジット計画」などの表現が使われ、投資家に資金回収の見通しを伝えます。
ピボット(Pivot)
定義・意味:
ビジネスモデルや製品戦略の大きな方向転換を指す言葉です。スタートアップが事業上の課題に直面した際、アイデアの核となる部分(軸足)は維持しつつ、それ以外の要素を大胆に変更する戦略的転換を意味します。
簡単に言えば「路線変更」で、新しい市場ニーズに合わせて事業内容を再構築することです。
IR資料での使われ方:
投資家向けには「○○事業にフォーカスするためピボットを実行した」といった形で報告されます。
IR資料ではピボットの結果として「市場適合性が向上し成長加速した」など、方向転換の成功を強調するケースが多いです。失敗を最小限に抑え柔軟に戦略変更できるスタートアップらしさとして捉えられます。
インキュベーター(Incubator)
定義・意味:
創業直後からシード期(種の段階)までのごく初期のスタートアップを支援する組織やプログラムです。新しいアイデアやビジネスモデルを「孵化(incubate)」させることに注力し、オフィススペース提供やメンタリング、少額の資金提供などで起業を手助けします。
IR資料での使われ方:
企業紹介や沿革の中で「〇〇インキュベーター出身」「インキュベーションプログラム採択企業」といった表現で登場します。これはそのスタートアップが有望と認められて支援を受けた実績として語られ、投資家への信用アピールにつながります。
アクセラレーター(Accelerator)
定義・意味:
スタートアップの成長を“加速”させることを目的にした支援プログラムや組織です。通常、プロダクトやサービスの種ができた後のシード期・アーリー期の企業を対象に、資金提供やメンタリング、ネットワーク紹介などを短期集中で行います。インキュベーターが「事業の孵化」なら、アクセラレーターは「事業の加速」と言えます。
IR資料での使われ方:
IRでは「当社は〇〇アクセラレーター出身である」と述べることで、優良なプログラムに採択された実績を示すことがあります。また決算説明等で「アクセラレーションプログラムを通じて事業拡大を図った」など成長のきっかけとして触れられることもあります。
2. プロダクト開発・エンジニアリング
MVP(Minimum Viable Product, 最小実用プロダクト)
定義・意味:
「実用最小限の製品」のことで、ユーザーに価値を提供できる最低限の機能だけを持った初期バージョンの製品を指します。
完璧さではなく必要最小の機能に絞ることで、早期に市場からフィードバックを得て、無駄な開発を避ける狙いがあります。
IR資料での使われ方:
投資家向けには「MVP開発によって市場の反応を検証しました」「MVP段階で◯◯人のユーザーを獲得しました」などと使われます。これは、リソースを効率的に使い検証したことを示し、ビジネスモデルの実現可能性や顧客ニーズの確認をアピールする文脈です。
プロダクト・マーケット・フィット(Product-Market Fit, PMF)
定義・意味:
開発した製品やサービスが、狙った市場のニーズにしっかり合致している状態を指します。ユーザーがそのプロダクトの価値を強く感じ、継続利用や支払いを厭わないような状況で、「市場に求められている証拠」が現れている段階です。PMFを達成すると急成長しやすいと言われます。
IR資料での使われ方:
IRでは「○年○月にPMFを達成し、ユーザー数が急増しました」のように、事業転換点として言及されます。投資家もPMFの有無を重要視するため、「当社サービスは市場に受け入れられた(=PMF達成)」という説明は、今後の成長見通しに説得力を持たせる材料として使われます。
アジャイル開発(Agile Development)
定義・意味:
ソフトウェア開発手法の一つで、小さな機能単位で素早く開発・リリースと改良を反復するスタイルです。計画に従ったウォーターフォール型と対照的に、アジャイル(敏捷)に変化へ対応し、チームで短いサイクル(スプリント)を回していきます。柔軟かつ迅速に製品を進化させられるのが特徴です。
IR資料での使われ方:
技術力や開発効率をアピールする際に「アジャイル開発手法を取り入れ、機能改良のスピード向上を図っています」と記載されます。投資家に対しては、環境変化やユーザーニーズに迅速に対応できる開発体制であることを示す文脈で使われ、経営の俊敏性を強調します。
スクラム(Scrum)
定義・意味:
アジャイル開発の具体的な実践フレームワークの一つです。
ラグビーのスクラムになぞらえ、小規模なチームがプロダクトオーナーやスクラムマスターの下で密なコミュニケーションをとり、短い期間で計画・実装・テストを繰り返します。タスクの可視化や振り返り(レトロスペクティブ)などのプロセスを重視します。
IR資料での使われ方:
スクラムそのものがIR資料に記載されることは稀ですが、開発スピードやチーム力を語る場面で「当社のエンジニアリング組織はスクラム開発によって○○を実現しています」と補足的に触れられることがあります。投資家に対し、効率的な開発管理体制を整えている印象を与える狙いです。
プロトタイプ(Prototype)
定義・意味:
製品やサービスの「試作品」「原型モデル」のことです。
実装前のデザインモックや簡易版アプリなど、完成版の前にユーザー検証や関係者のフィードバックを得るために作られるものを指します。プロトタイピングによって、早期に問題点を洗い出し、開発リスクを下げることができます。
IR資料での使われ方:
事業計画の説明時に「プロトタイプ段階でユーザーから高評価を得ました」「プロトタイプを使ったPoC(概念実証)を完了しました」などと使われます。投資家はそれによって、アイデアが具体化され実験済みである点や、製品化への見通しが立っていることを理解します。
技術的負債(Technical Debt)
定義・意味:
開発スピードを優先するあまりに生じた不完全なコードやシステム設計上の課題のことです。本来必要なリファクタリング(整理)や最適化を後回しにした「借金」に例えられ、放置すると将来的に開発効率の低下や不具合頻発という利息を支払う羽目になります。
IR資料での使われ方:
IRでは直接言及されることは少ないですが、プロダクトの改善投資を説明する際に「技術的負債の解消に取り組んでいます」と触れることがあります。これは将来の開発効率向上やサービス安定性のための投資であると伝え、短期利益より長期成長を重視している姿勢を示す文脈です。
A/Bテスト(A/B Testing)
定義・意味:
ユーザーの反応を比較するために、機能やデザインが異なる2パターン(AとB)の施策を同時に試す手法です。例えばWebサイトのボタン色を変えたバージョンAとBを一定割合のユーザーに表示し、クリック率などの差異を測定します。どちらがより成果を出すか検証し、データに基づき意思決定するためのアプローチです。
IR資料での使われ方:
サービス改善の具体策として「当社はA/Bテストを重ねてUIを最適化し、コンバージョン率を向上させています」と紹介されます。これにより、データドリブンで継続的改善をしている企業文化をアピールできます。投資家には、科学的手法でユーザーエンゲージメントを高めている点として評価されます。
DevOps(デブオプス)
定義・意味:
開発(Development)と運用(Operations)を一体化して行う手法・文化のことです。開発チームと運用チームの連携を密にし、自動化ツールなどを活用してコードのビルド・テスト・デプロイを継続的に行います。その結果、ソフトウェアのリリースを高頻度かつ安定して行えるようになります。
IR資料での使われ方:
技術力やサービス安定性の訴求として「DevOps体制によりリリースサイクルを短縮」「サービスの稼働率向上に成功」といった説明がされることがあります。これは、インフラ運用と開発の効率化により競争優位を築いていることを示し、投資家に安心感を与える材料となります。
3. ビジネスモデル・資金調達
ベンチャーキャピタル(Venture Capital, VC)
定義・意味:
成長が見込まれる未上場企業(スタートアップ)に対し、株式投資を通じて資金提供する投資ファンド/会社です。VCは高リスク・高リターンを狙い、経営支援やネットワーク紹介など非財務的サポートも行います。出資と引き換えに株式を取得し、企業がIPOやM&Aする際の売却益(キャピタルゲイン)で収益を上げます。
IR資料での使われ方:
「〇〇ベンチャーキャピタルよりシリーズAで資金調達」といった形で登場します。どのVCが出資しているかは信頼性の指標となり、IRでは有力VCからの出資を実績として記載します。また、「VC出資比率〇%」など株主構成としても示され、ガバナンスや資金力の裏付けとして注目されます。
エンジェル投資家(Angel Investor)
定義・意味:
創業間もないスタートアップに対し、個人として資金提供を行う富裕投資家のことです。天使のようにリスクマネーを提供してくれる存在という意味で「エンジェル」と呼ばれます。
少額出資が多いですが、経営者のメンタリングや人脈紹介など、資金以外の支援を行うケースもあります。
IR資料での使われ方:
資金調達の履歴紹介で「創業期にエンジェル投資家から出資を受けた」と記載されることがあります。またIR上では直接名前が出なくとも、株主構成説明で「主要株主:創業者〇〇氏○%、エンジェル投資家△△氏○%…」のように示され、会社成長初期にサポートした人物として位置付けられます。
シードラウンド(Seed Round)
定義・意味:
スタートアップが創業直後に実施する初期段階の資金調達のことです。「シード(種)」の名の通り事業の種を育てるための投資ラウンドで、調達額は比較的小規模。出資者はエンジェル投資家やシード特化VC、事業会社のCVCなどが多く、資金はプロトタイプ開発や市場調査、人材確保に使われます。
IR資料での使われ方:
会社概要や沿革で「20XX年○月 シードラウンドで○○万円を調達(出資:△△等)」と紹介されます。投資家に対して、創業期から出資者が付いていることや事業が順調に進んでいることを示す材料になります。また、「シード期」という言葉でステージを説明し、事業成熟度の目安として言及する場合もあります。
シリーズA・B・C(Series A/B/C Round)
定義・意味:
シードの次に来る、複数回にわたる資金調達ラウンドの呼称です。シリーズAはプロダクトやサービスが軌道に乗り始めた段階での本格的な大型調達、第2弾がシリーズB、第3弾がシリーズC…とアルファベット順に続きます。各ラウンドで企業評価額(バリュエーション)が上がっていくのが一般的です。
IR資料での使われ方:
プレスリリースやIR資料で「シリーズAで○億円、シリーズBで○億円を調達」という形で具体的な調達額とともに報告されます。例えば「2025年にシリーズB(評価額50億円)を実施」などと書かれ、事業成長に応じた調達ステージと企業価値の伸長を示す指標となります。
ピッチデック(Pitch Deck)
定義・意味:
スタートアップが投資家に事業計画を説明するための資料(プレゼンテーションスライド)のことです。10〜20枚程度にビジネス概要・課題と解決策・市場規模・ビジネスモデル・チーム・財務予測などをまとめます。投資獲得の勝負資料であり、分かりやすさとストーリー性が重視されます。
IR資料での使われ方:
未上場企業では「ピッチコンテストで最優秀ピッチデック賞を受賞」などと実績紹介されることもあります。上場企業でも、投資家説明会資料を指して「当社のピッチデックにて詳細を開示しています」といった言及が見られます。投資家はピッチデックを通じて企業のビジョンや戦略を読み取るため、その完成度が評価材料になります。
デューデリジェンス(Due Diligence, DD)
定義・意味:
投資実行前に行われる徹底的な調査・分析のことです。財務状況やビジネスモデルの健全性、法務・知財面のリスク、人材や技術力など、多方面から投資対象企業を評価します。投資判断の裏付けを取る作業で、日本語では「適正評価」や「精査」と言われます。
IR資料での使われ方:
上場企業の場合、M&A発表時に「現在デューデリジェンスを実施中」などと表現されます。またスタートアップの資金調達においては、「弊社はVCからのデューデリジェンスを経てシリーズA出資を受けました」といった形で使われ、投資家に対し「第三者から入念に評価された会社」であることを示すニュアンスがあります。
IPO(Initial Public Offering, 新規株式公開)
定義・意味:
企業が証券取引所に上場し、株式を一般投資家に公開・販売することです。
スタートアップにとって最大のエグジット(出口)手段の一つであり、IPOにより広く資金調達が可能になるほか、企業の信用力向上や知名度向上などのメリットがあります。ただし上場審査や開示義務などハードルも高いです。
IR資料での使われ方:
「当社は〇年以内のIPOを目指しています」「東京証券取引所グロース市場へIPOを果たしました」などとIRで語られます。IPO計画は投資家にとって出資回収の重要イベントなので、ロードマップとして示されることが多いです。また、上場後のIRでは「IPO時の公募価格」「IPOプロセスで得た資金の使途」などの情報も提供されます。
4. 財務・KPI指標
KPI(Key Performance Indicator, 重要業績評価指標)
定義・意味:
企業や事業の目標達成度を定量的に測るための主要な指標です。売上高やユーザー数のような成果を示す数値で、経営目標(ゴール)に直結するものを選定します。KGI(重要目標達成指標)に対する途中経過の指標とも位置づけられ、複数のKPIをモニタリングして健康状態を把握します。
IR資料での使われ方:
IRでは「主要KPIの推移」としてグラフや表で定量情報を示すのが一般的です。例えば「KPI:月次売上成長率○%」「KPI:有料会員数○万人」等が記載され、投資家は事業の進捗や成長性を判断します。また決算説明で「当四半期はKPI達成に向け順調」とコメントするなど、経営陣が自社の指標管理を強調する際にも使われます。
ARR(Annual Recurring Revenue, 年間経常収益)
定義・意味:
主にSaaS企業で用いられる指標で、サブスクリプション(月額課金など)の年間ベースの経常的収益を示します。月次経常収益(MRR)の12倍で計算されることが多く、一定時点における契約から得られる将来12か月分の収益額を表します。新規契約や解約の影響を反映するため、成長率も重要です。
IR資料での使われ方:
決算資料で「ARR○億円(前年同期比○%増)」という形で公表されます。特にサブスク型ビジネスではARRは規模感と成長性を示す代表的な数値として投資家が注目します。IRではグラフ付きでARRの継続的な伸びを示し、「収益基盤が順調に拡大している」ことをアピールする材料となります。
MRR(Monthly Recurring Revenue, 月次経常収益)
定義・意味:
こちらもサブスクリプションモデル企業で重要な指標で、1か月あたりの経常収益を示します。ある月における定期課金や契約から得られる収益の合計で、新規獲得や解約により毎月変動します。MRRの推移を見ることで、事業の直近トレンド(増加・減少傾向)を把握できます。
IR資料での使われ方:
「当月MRRは◯◯万円で順調に増加」というように月次開示するスタートアップもあります。投資家に対しては、ARRと合わせて短期的な成長ペースを示すために使われます。また、IRでは「MRR拡大に伴いキャッシュフローも改善」という説明で、安定収益の積み上げが財務健全性に寄与していることを伝えるケースもあります。
CAC(Customer Acquisition Cost, 顧客獲得コスト)
定義・意味:
新規顧客1人(または1社)を獲得するためにかかった平均コストです。マーケティング広告費や営業人件費など、見込み客発掘から契約獲得までに要した総費用を、新規顧客数で割って算出します。CACは小さいほど効率的な獲得ができていることを意味し、ビジネスの採算性や拡張性に影響します。
IR資料での使われ方:
「当社のCACは◯◯円で、業界平均を下回っています」のようにIRで触れられることがあります。これは効率的に顧客を増やせている強みとしてアピールされます。また、LTVとの対比で「LTV/CAC比◯倍」という形で記載され、1人当たり生涯価値が獲得コストの何倍かを示すことで、成長投資の妥当性を投資家に示します。
LTV(Life Time Value, 顧客生涯価値)
定義・意味:
1人の顧客が生涯に企業にもたらす利益(または売上)の総額です。平均購入単価や購入頻度、契約継続期間などから算出されます。サブスク企業では「平均月額課金 × 平均契約月数」などで求め、LTVが高いほど一顧客あたりから長期的に大きな価値を得ていることを示します。
IR資料での使われ方:
IRでは「当社サービスのLTVは◯万円」という形で提示されることがあります。特にCACとの関係で注目され、「LTVはCACの◯倍」という数字が示されれば、投資回収力が高く健全なビジネスと評価されます。投資家はLTVが高くCACが低いモデルを好むため、両指標のバランスが強調されます。
チャーンレート(Churn Rate, 解約率)
定義・意味:
サブスクリプションモデルなどで一定期間内に顧客が離脱(解約)した割合を示す指標です。例えば「月次チャーンレート5%」であれば、前月比で5%の顧客が契約終了したことを意味します。
顧客離脱率とも呼ばれ、逆指標として継続率(リテンション率)を用いる場合もあります。チャーンレートは低いほど望ましく、安定収益の維持に重要です。
IR資料での使われ方:
SaaS企業のIRでは「月次チャーンレートを◯%に抑制しています」「チャーン低減施策により解約率改善」といった表現で登場します。投資家はチャーンが高すぎると将来の成長に黄信号と捉えるため、IRではチャーン率の推移や改善施策を報告し、顧客維持に努めている点をアピールします。
バーンレート(Burn Rate)
定義・意味:
企業が月間に消費する資金の額、いわば現金燃焼速度を指します。特に赤字スタートアップでは毎月のキャッシュ流出量を示し、「月次◯百万円のバーンレート」などと使われます。バーンレートが高いほど手元資金が早く減るため、資金繰りに与える影響が大きくなります。
IR資料での使われ方:
投資ラウンド実施時に「現在のバーンレートは◯◯万円で、調達資金によりさらに◯ヶ月の事業継続が可能」といった説明がなされます。投資家に対し、調達額の妥当性や資金の持続期間を示すために用いられます。また、経営効率化を述べる際に「バーンレートの削減に成功」という表現でコスト管理の成果を伝えることもあります。
ランウェイ(Runway)
定義・意味:
手元資金であと何ヶ月事業運営できるかを示す指標です。直近のバーンレートから計算され、例えば「ランウェイ12ヶ月」は、今の支出ペースで1年後に資金が尽きることを意味します。飛行機が離陸するまでの滑走路になぞらえており、資金が尽きる前に次の資金調達や黒字化といった離陸が必要になります。
IR資料での使われ方:
スタートアップの資金計画説明で「現在の資金でランウェイはあと◯ヶ月」と明示されることがあります。投資家に対し、現状の財務余力と今後の資金調達タイミングを示唆するものです。ランウェイが短すぎる場合はリスク要因として指摘されるため、IRでは「調達によりランウェイ延伸」といった形で安心感を与える説明がされます。
MAU(Monthly Active Users, 月間アクティブユーザー)
定義・意味:
1ヶ月間にサービスを利用したユニークユーザー数を示す指標です。SNSやゲーム、Webサービスなどで利用され、サービスの規模感や熱量を測る代表的なユーザーベース指標です。類似指標に日次アクティブユーザー(DAU)や週間アクティブユーザー(WAU)があり、これらを組み合わせてエンゲージメントを分析します。
IR資料での使われ方:
「MAU○万人(前年同月比○%増)」のように、ユーザー規模の実績としてIR資料で強調されます。投資家はMAUの成長率から市場浸透度や利用頻度を評価します。また「DAU/MAU比」(いわゆる粘着率)を開示し、ユーザーの定着度合いを示すケースもあります。MAUは事業の勢いを直感的に伝える重要な数字として扱われます。
ARPU(Average Revenue Per User/ユーザーあたり平均売上)
定義・意味:
1ユーザーあたりが一定期間(通常は月または年)にもたらす平均売上を示す指標です。
SaaSやアプリサービスなどで一般的に使われ、「MRR ÷ 有料ユーザー数」で算出します。
ARPUが高いほど単価が高い、つまり顧客ごとの収益性が高いことを意味します。
IR資料での使われ方:
投資家に対して「顧客単価の向上」「アップセルの成果」「価格改定効果」を定量的に示すために使われます。
たとえば「ARPUが前年同期比+15%」と提示することで、単価上昇による収益改善を分かりやすく伝えることができます。
また「MAU(アクティブユーザー数)」と掛け合わせて「ARPU×MAU=売上規模」の関係を説明するケースも多いです。
ARPA(Average Revenue Per Account/アカウントあたり平均売上)
定義・意味:
1契約アカウント(法人単位など)あたりの平均月次売上を表す指標で、B2B SaaSでよく用いられます。
計算式:「MRR ÷ 有料アカウント数」
B2CのARPUと異なり、「1社あたりの契約額」や「部署ごとの契約単価」の把握に役立ちます。
IR資料での使われ方:
BtoB型企業のIRでは「ARPA上昇=単価成長」として重要指標になります。
たとえば「エンタープライズ比率の上昇によりARPAが20%増加」など、顧客ポートフォリオの質的向上を示す材料になります。
また、「ARR(年間経常収益)」との関係を明示して「ARR=ARPA×契約社数×12」のように整理すると、売上ドライバーの構造が明確になり、投資家に理解されやすくなります。
TAM(Total Addressable Market/ターゲット総市場)
定義・意味:
企業が提供する製品・サービスが理論的に到達し得る「最大の市場規模」を指します。
つまり、「世界中の潜在顧客全員に販売できた場合の売上総額」を表す概念で、最も広義の市場です。
TAMはトップダウン(業界全体の統計から推定)またはボトムアップ(単価×想定顧客数)で算出します。
IR資料での使われ方:
投資家に対して「この市場にはまだ大きな成長余地がある」と示すために活用されます。
たとえば「当社のTAMは1兆円規模」と記載することで、事業のスケーラビリティや市場の大きさを直感的に伝えます。
ただし「理論値」であるため、現実的な市場獲得可能性と区別して説明するのがポイントです。
SAM(Serviceable Available Market/到達可能市場)
定義・意味:
TAMの中で、自社の提供エリアやサービス仕様、顧客層などの制約を踏まえ、実際に狙うことができる市場規模を示します。
たとえばTAMが「世界全体」であっても、日本国内に限定した市場をSAMと定義するケースが一般的です。
IR資料での使われ方:
中期経営計画などで「当社がまずターゲットとする市場はTAMのうちの○○億円規模」と具体的に示す際に用います。
投資家に対して「現実的なターゲット市場」を明示することで、戦略の実効性と信頼性を高める役割を果たします。
SAMを明確にすることで、「参入余地」や「集中戦略」の説得力が増します。
5. AI/データ活用
人工知能(Artificial Intelligence, AI)
定義・意味:
コンピュータに人間の知能のような推論・学習・判断能力を持たせる技術全般を指します。機械学習やルールエンジンなど様々な手法を含む広義の概念で、近年では特にディープラーニングなどの進歩により画像認識や自然言語処理などで人間同等かそれ以上の性能を発揮するAIが登場しています。
IR資料での使われ方:
IRでは自社技術の先進性を示すため「AI技術を活用した○○システム」などと記載されます。投資家にとってはキーワード的存在で、「AIを活用している企業=革新的」という印象を与えます。そのためプレゼン資料等でも「当社サービスはAIによる自動化を実現」と強調するケースが増えています。
機械学習(Machine Learning)
定義・意味:
人工知能の一分野で、コンピュータが大量のデータからパターンを学習し、明示的にプログラムされなくても予測や判断ができるようにする手法です。統計的アルゴリズムを用いてモデルを訓練し、新しいデータに対して推論を行います。スパム判定や需要予測、レコメンド(推薦)機能など幅広く使われています。
IR資料での使われ方:
自社プロダクトの優位性説明で「機械学習アルゴリズムにより精度向上」「Machine Learningモデルを活用した高度な分析」といった記述が登場します。投資家には技術的ハードルの高さやデータ活用力をアピールする意味があり、「単なる手作業でなく機械学習で自動最適化している」という点が評価ポイントとなります。
ディープラーニング(Deep Learning)
定義・意味:
機械学習の中でも多層ニューラルネットワークを用いた手法群を指します。脳の神経回路を模した構造で、大量のデータから特徴を自動抽出し、高い精度で画像・音声認識や自然言語処理を可能にしました。ディープラーニングの登場によりAI性能が飛躍的に向上し、第二次AIブームの原動力となりました。
IR資料での使われ方:
技術説明で「当社独自のディープラーニングモデルを活用しています」といった表現が使われます。例えば画像解析サービスのIRでは「ディープラーニングにより識別精度99%を実現」等と記載し、最先端AI技術の採用を強調します。専門用語ではありますが、投資家も昨今のAIブームで馴染みがあるためPRポイントとして積極的に用いられます。
ビッグデータ(Big Data)
定義・意味:
従来の手法では処理が困難なほど巨大かつ多様なデータ群を指します。具体的には5V(Volume大量・Velocity高頻度・Variety多様・Veracity真偽・Value価値)が特徴と言われ、例としてSNSの膨大な投稿データやIoTセンサーから集まるリアルタイムデータなどがあります。ビッグデータは高度な分析により新たな知見や付加価値を生み出します。
IR資料での使われ方:
「ビッグデータ解析に強み」「当社サービスはビッグデータを活用して○○を実現」といったフレーズでIRに登場します。投資家には、蓄積された大量データ資産を活用して競争優位を得ている印象を与えます。例えば「数百万件のビッグデータからユーザー行動を分析し、精緻なマーケティングを可能にする」など、事業価値の源泉として説明されます。
データドリブン(Data-Driven)
定義・意味:
意思決定や施策実行を勘や経験ではなくデータに基づいて行う考え方・手法のことです。「データドリブン経営」「データドリブンマーケティング」のように使い、定量的な分析結果を重視してビジネスを進める姿勢を表します。組織文化として根付いている場合、「データ駆動型の意思決定」とも表現されます。
IR資料での使われ方:
IRでは経営方針や強みの説明で「当社はデータドリブンなアプローチで市場ニーズに対応しています」と記載されます。これは、客観的データに裏打ちされた戦略遂行により成功確度が高いことをアピールするものです。また具体例として「データドリブンマーケティングによりCACを改善」など、成果につなげている点を強調します。
生成AI(Generative AI)
定義・意味:
文章や画像など新たなコンテンツを生成するAI技術の総称です。大規模言語モデル(LLM)によるチャットbot(例: ChatGPT)や、画像生成AI(例: Stable Diffusion)などが代表例です。大量データで訓練されたモデルが創造的なアウトプットを生み出せる点が特徴で、2020年代に入り急速に普及・発展しています。
IR資料での使われ方:
最新トレンドとして、「当社は生成AIを活用し業務効率化を図っています」や「生成AI関連サービスを開発中」といった記載が増えています。投資家へのメッセージとしては、最先端技術にキャッチアップし競争力を高めているアピールです。生成AIは注目ワードのため、事業戦略説明や今後の展望の箇所で取り上げられることが多いです。
アルゴリズム(Algorithm)
定義・意味:
特定の問題を解くための手順や計算方法のことです。プログラムにおいて「どのように処理を行うか」の論理的な流れを指し、AIに限らずソートや検索からレコメンドエンジンまで幅広い分野で使われる基本概念です。優れたアルゴリズムは処理効率や結果精度に大きな差を生みます。
IR資料での使われ方:
自社技術を説明する中で「独自アルゴリズムによって他社比○倍の精度を実現」などと登場します。投資家に対してはブラックボックスな技術部分を端的に示す言葉として機能し、「アルゴリズム=他社には真似できないコア技術」というニュアンスで語られることもあります。ただし具体的内容は機密である場合が多く、「特許取得済のアルゴリズム」程度の表現に留まります。
6. マーケティング/SNS/グロース
グロースハック(Growth Hacking)
定義・意味:
製品やサービスのユーザー数や売上を急激に成長(グロース)させるために、データ分析やマーケティング・開発のテクニックを駆使して改善を繰り返す手法・考え方です。エンジニアリングとマーケティングの境界を越えて、「成長」に直結するあらゆる工夫(ハック)を実施します。小さな実験を積み重ねて、爆発的なユーザー増加を狙います。
IR資料での使われ方:
スタートアップ特有の強みとして「グロースハック文化」をアピールする場面があります。「グロースハックチームを組成し、プロダクトの継続的な成長施策を実行中」などと記載され、投資家に対しては成長ドライバーを意識的に持っていることを伝えます。また、短期間でユーザー○倍増といった成功事例とセットで語られることもあります。
バイラル(Viral, バイラルマーケティング)
定義・意味:
ウイルスの拡散になぞらえ、ユーザーが自発的にサービスを拡散してくれる現象や、その仕掛け(バイラルマーケティング)を指します。口コミや紹介プログラム、SNSでのシェア等により、広告費をかけずともユーザーがユーザーを呼ぶ連鎖的な成長が起こる状態です。バイラル係数(1人のユーザーが新規ユーザーを何人呼ぶか)で効率を測ることもあります。
IR資料での使われ方:
「バイラル効果でユーザー数が拡大」といった表現が見られます。例えば「紹介コード施策によりバイラル成長を実現し、月間新規ユーザーの30%が既存ユーザー経由に」というように、投資家に対し成長の自走が起きている点を強調します。バイラルは低コストでの急成長を示唆するため、IR上で示されればポジティブな要素として受け取られます。
ネットワーク効果(Network Effect)
定義・意味:
あるサービスのユーザー数が増えるほど、そのサービスの価値が指数的に高まる現象です。典型例はSNSやマーケットプレイスで、ユーザーが増える→利便性向上→さらにユーザーが増える、という好循環が生まれます。ネットワーク効果が強いビジネスは、一度軌道に乗ると競合が参入しづらくなり、独占的地位を築きやすい特性があります。
IR資料での使われ方:
優れたビジネスモデルの説明で「当社サービスには強力なネットワーク効果が存在します」と触れることがあります。投資家向けには、「ユーザー数○万人で臨界点を超え、一気に拡大した」とか「ネットワーク効果によりユーザーあたり獲得コストが逓減している」などと説明し、成長の持続性や市場支配力をアピールします。
SEO(Search Engine Optimization, 検索エンジン最適化)
定義・意味:
Googleなど検索エンジンで自社サイトやコンテンツを上位表示させるための施策全般を指します。キーワード調査やサイト構造の改善、コンテンツ充実、被リンク獲得などを通じて検索順位を上げ、オーガニック流入(広告費をかけない集客)を増やすマーケティング手法です。
IR資料での使われ方:
ユーザー獲得戦略の一環として「SEO強化により新規ユーザーの流入数が増加」と報告されることがあります。たとえば「SEO経由のサイト訪問者が前年同月比○%増」など具体的な成果とともに記載され、投資家に対しては効率的な集客努力が実っていることを示します。また、広告費削減効果の説明で「SEOに注力しCAC改善」といった使われ方もします。
エンゲージメント(Engagement)
定義・意味:
一般にはユーザーや顧客がサービスやブランドに対して示すロイヤリティや積極的な関与度合いを指します。具体的には利用頻度や滞在時間、リアクション(「いいね!」やコメント)、リピート購入率などで測られ、高いエンゲージメントは熱量の高いファンが多い状態を意味します。SNSでは投稿への反応率、アプリでは継続利用日数などが指標となります。
IR資料での使われ方:
「ユーザーエンゲージメント向上のため機能拡充を行った」「エンゲージメント指標であるDAU/MAU比が改善している」などと使われます。投資家にとってエンゲージメントは、ユーザー基盤の質を知る手がかりです。IRでは「エンゲージメントが強固=解約されにくい」という文脈で語られ、将来の収益安定性を示すポジティブ材料として提示されます。
コンバージョン率(Conversion Rate)
定義・意味:
Webサイトやアプリ上で、訪問者のうち特定の成果(購入・会員登録・資料請求など)に至った割合を指します。例えばECサイトで100人中5人が購入すればCVR(Conversion Rate)は5%です。マーケティングにおいて重要な効率指標で、UI改善やキャンペーン施策によってこの率を上げることが収益拡大に直結します。
IR資料での使われ方:
業績向上要因の説明で「サイトのコンバージョン率向上により売上増」と言及されることがあります。投資家に対しては「少ないトラフィックでも高い転換率で効率よく収益化できている」ことや、「コンバージョン率改善施策が成功しマーケティングROIが向上した」といった形で語られ、経営効率の良さを示すポイントになります。
リテンション率(Retention Rate)
定義・意味:
一定期間後にサービスを継続利用しているユーザーの割合、つまり顧客維持率を意味します。新規顧客がどれだけ定着したかを見る指標で、1ヶ月リテンション率が50%なら「獲得から1ヶ月後に半数がまだ利用」。サブスクでは契約継続率、アプリでは30日リテンション率などが使われ、リテンション率が高いほど顧客忠誠度が高いと言えます。
IR資料での使われ方:
IRでは「〇ヶ月後リテンション率○%を達成」といったデータで顧客の定着度を示すことがあります。投資家はリテンション率が高いビジネスほど安定した収益が見込めると判断するため、「リテンション率向上の施策によりLTVが伸長」といった説明はポジティブに受け取られます。チャーンレートと併せて報告し、顧客動向を総合的に説明するケースもあります。
7. 組織・人事・カルチャー
ストックオプション(Stock Option)
定義・意味:
企業が役職員に対してあらかじめ定めた価格で自社株を購入できる権利を付与する制度です。現時点の株価より低い価格で将来株式を取得できるため、自社の企業価値向上が利益になります。スタートアップでは、資金に余裕がない中で優秀な人材を惹きつける報酬手段や、従業員のモチベーション向上策として広く用いられています。
IR資料での使われ方:
上場企業でも「新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ」としてIRリリースされます。スタートアップの説明では「創業メンバーにストックオプションを付与し、インセンティブ設計している」と紹介され、投資家にはチームのコミットメント強化策として伝えられます。また、潜在株式数や希薄化率として財務数値にも影響するため、IRでその概要が説明されることも重要です。
OKR(Objectives and Key Results)
定義・意味:
目標(Objective)と主要な結果(Key Results)をセットで設定し、組織と個人の成果を管理する目標管理手法です。Googleが採用したことで有名になりました。野心的な定性的目標と、測定可能な3〜5つ程度の結果指標を定め、四半期ごとなどのサイクルで進捗をチェックします。組織全体の方向合わせと高い目標達成を促すフレームワークです。
IR資料での使われ方:
組織文化の先進性を示す文脈で「当社はOKRを導入し、社員一人ひとりが野心的な目標に取り組んでいます」と記載されます。これは、透明性ある目標管理によって社員のパフォーマンスを最大化しているとアピールするものです。投資家に対しては、強力な実行力と一体感のある組織であることを示唆し、成長実現性を裏付ける要素として映ります。
ダイバーシティ&インクルージョン(Diversity & Inclusion, D&I)
定義・意味:
職場における多様性の受容と包摂を推進する考え方です。性別・人種・国籍・年齢・専門性など様々なバックグラウンドを持つ人材を受け入れ(ダイバーシティ)、その全員が活躍できる環境を整える(インクルージョン)ことを指します。イノベーション創出や企業の社会的価値向上の観点から近年重視されています。
IR資料での使われ方:
サステナビリティやESG情報の一環として「D&I推進」を掲げる企業が増えています。IRでは「女性管理職比率◯%」「外国籍社員◯名」といったデータを開示し、「ダイバーシティ経営により多角的な視点を事業に活かしている」とアピールします。投資家はD&Iを企業の長期的成長基盤と見なす傾向があり、その取り組みが評価対象となります。
オンボーディング(Onboarding)
定義・意味:
新しく組織に加わった社員がスムーズに職場に適応し、戦力化するまでのプロセスや支援活動を指します。具体的には入社時研修やメンター制度、最初のプロジェクトへのアサインなどを通じて、新人が企業文化や業務に馴染む手助けをします。オンボーディングが整っていると立ち上がりが早く、早期離職の防止にもつながります。
IR資料での使われ方:
人材戦略の説明で「充実したオンボーディングプログラムにより人材の早期活躍を実現」と言及される場合があります。投資家にとって、人材育成・定着は企業価値向上の重要要素なので、オンボーディングの整備は優秀な人材確保と活用の裏付けとして映ります。また離職率低減策の一環として紹介され、「従業員エンゲージメント向上」に寄与していると強調されることもあります。
カルチャーフィット(Culture Fit)
定義・意味:
採用やチーム編成において、その人の価値観や働き方が会社の文化・理念に適合しているかどうかを指す言葉です。スタートアップではスキル以上に重視されることも多く、「カルチャーフィット」している人材は組織内で協調・活躍しやすいと考えられます。一方で多様性とのバランスも課題となり得る概念です。
IR資料での使われ方:
直接IRに登場する頻度は高くありませんが、経営陣インタビューや説明会で「採用ではスキルと同様にカルチャーフィットを重視している」と述べられることがあります。これは、組織が内包する独自のカルチャー(例:挑戦を歓迎する文化)を守りつつ成長していることをアピールします。投資家に対しては、社内文化が一貫して強みになっている企業であることを示す文脈です。
どうでしたでしょうか?
記事自体は生成AIにかなりアシストしてもらって書きました。
オンライン会議の際にそっと開いて、わからない言葉がでてきたらさっと調べる。
そんな使い方をしてください!