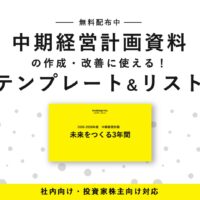マコトは、上場企業のCEO。
この数年、ESGやサステナビリティの必要性を感じながらも、最近耳にする「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」や「ダブルマテリアリティ」という言葉には、どこかモヤモヤが残っていた。
「これは単なる流行り言葉なのか? それとも、本当に経営を変える鍵なのか?」
そんな疑問を抱えながら、マコトはいつものように相談相手であるジュン博士を訪ねた。
ダブルマテリアリティは「地図」、SXは「旅」
ジュン博士、本日も少しご相談させていただけますか?
最近、“SX”や“ダブルマテリアリティ”という言葉をよく耳にするのですが、正直なところ、本質が見えてこなくて…。
ふむ、SXじゃね。
マコト、それは“旅”のようなものだよ。
旅、ですか? 会社が旅に出るということでしょうか。
そう。企業を持続可能な姿へと変えていく長い旅路さ。
だが、旅に出るならまず必要なものがあるだろう?
……地図、ということですか?
その通り。SXという旅に出るには、まず“ダブルマテリアリティ”という名の地図が必要なんだ。
ダブルマテリアリティとは?
ダブルマテリアリティ・・・言葉としては知っているのですが、正直、しっかりとは理解できておりません。どのような意味なのでしょうか?
良い質問だね。簡単に言えば、「企業にとって何が重要課題(マテリアリティ)か」を、2つの視点から捉える考え方だ。
1つ目は「財務マテリアリティ」。
これは従来からある考え方で、「企業の財務や成長に影響を及ぼすかどうか」で重要性を判断する。投資家にとって“重要な情報”かどうかという視点だね。
2つ目が「インパクトマテリアリティ」。
こちらは「企業が社会や環境に与える影響」に注目する。
たとえそれが直ちに企業の業績に影響しなくても、社会に大きなインパクトをもたらすなら、それは“重要課題”とみなすわけだ。
なるほど…つまり、投資家と社会、両方の目線から「何が大事か」を捉えようということですね。
マテリアリティを特定している企業も多いです。ダブルとの違いは?
ふむ。これまで主流だったのが「シングルマテリアリティ」だ。
こちらは“企業の利益や価値に影響するかどうか”、もしくはEGSだけの目線という一方向の視点だけでマテリアリティを見ていた。
でも今は、企業活動が社会や環境と密接につながっている時代だろう?
だから、企業にとって重要なことは「社会に与える影響でもあり、将来的に企業の財務にも返ってくる」。
それを両面から捉えるのがダブルマテリアリティなんだ。
なるほど…。当社でも数年前にマテリアリティを定義したのですが、実は「財務的に重要なこと」と「社会的に意義のあること」が混在していて、あまり明確に区別していないのです。
そうした状態でも問題ないのでしょうか?
そのような企業は実際とても多い。いわば「シングルマテリアリティのハイブリッド状態」だね。
しかし、そのままではどの課題がどの視点から重要なのかが曖昧になってしまう。
たとえば「人材開発」や「気候変動対応」といったテーマは、
財務にも関わるし、社会的責任としても意味がある。
こうした項目を一括りにしたままだと、「なぜそれが経営課題なのか」が社内外に伝わりづらくなる。
なるほど。
ダブルマテリアリティに仕訳けることで、優先順位や取り組みの根拠が明確になる。
だからこそ、既存のマテリアリティを“財務”と“社会インパクト”で整理し直すことが重要なんですね。
サステナビリティは「いいことをする」だけじゃない
ダブルマテリアリティについてはわかりました。
ただ、そうした社会的インパクトは、いわば“良いことをしている”という印象もありまして…。
本当に企業価値と関係しているのかと、少し疑問にも感じておりました。
それは確かに誤解されがちだね。
社会的インパクトは、中長期で“財務リスク”や“機会”に化ける可能性がある。
たとえば──
サプライチェーンで人権侵害 → 報道 → 不買運動
水不足 → 工場停止 → 収益減少
CO₂排出多 → 炭素価格の高騰 → コスト増
つまり、社会課題に向き合うことは、企業価値を守ることなんだ。
「いいことをする」ためじゃなくて、「会社を生き残らせるため」に必要なんだよ。
結果、社会にいい影響があるといいね。
SXとは“経営の旅路”である
なるほど。ではSXとは、そうした課題に対応するための取り組みということになるのでしょうか。
そうじゃな。
SXは、マテリアリティで特定した課題をもとに、事業や経営そのものを変革させるプロセスなんだ。
たとえば──
「気候変動対応」がマテリアリティ → 脱炭素型の製品開発や、再エネへの投資
「人材開発」がマテリアリティ → リスキリングプログラムの導入や評価制度改革
そしてこれらを中期経営計画(中計)に落とし込む。ここが肝心だ。
たしかにおっしゃる通りです。マテリアリティを掲げるだけでは、戦略としては弱いですね。中計と結びついてこそ実効性が出る。
その通り。ダブルマテリアリティは経営の地図。中計は航路。SXは旅そのものなんじゃ。
どのように開示するか?
こうした“地図と旅”の関係性は、報告書ではどのように表現するのが良いのでしょうか?
統合報告書では、「マテリアリティと経営戦略とのつながり」を一覧やマトリクスで見せるといい。
たとえばこんな具合にね
「なぜそれが重要なのか」「どう経営に活かすのか」「何で測るのか」をセットで見せることがポイント。
| マテリアリティ | 中計施策 | KPI |
| 脱炭素経営 | 再エネ導入拡大 | Scope1,2排出量削減率 |
| 人材戦略 | リスキリング強化 | 研修時間、従業員満足度など |
| 地域共生 | 地域事業との連携推進 | 拠点数、地元調達率、投資額など |
接続されていることがよくわかります!!
SXの旅へ歩き出す
ありがとうございます。SXというのは、単なる開示義務ではなく、選ばれ続ける企業になるための変革だと理解できました。
うむ。サステナビリティはコストではない。
それは未来への競争力そのものであり長い旅だよ。
そしてダブルマテリアリティはその地図。
まずは“地図”を整えて、我々の中期経営戦略ときちんと接続するところから始めてみます!
マコトは、静かに立ち上がった。
これまで断片的に理解していた「ダブルマテリアリティ」と「SX」が、一本の線でつながった今、目の前に広がる視界が明らかに変わった気がしていた。
自社の掲げるマテリアリティ。
それは単なるスローガンではなく、企業の進むべき方向を示す地図であり、そこに描かれた道筋を「経営戦略」として実装していくことが、自分の責務なのだと感じた。
まずは既存の課題を財務と社会の視点で再整理し、見落としてきたインパクトに光を当てる。
中期経営計画と照らし合わせながら、優先順位を明確にし、実行に移す。
「これは、未来の競争力そのものだ。」
そう確信したマコトの表情には、迷いはなかった。
ダブルマテリアリティという地図を手に、
マコトは、自らの会社を持続可能な未来へと導く旅路に、一歩を踏み出そうとしていた。


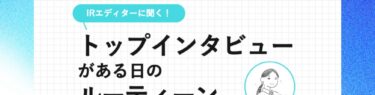





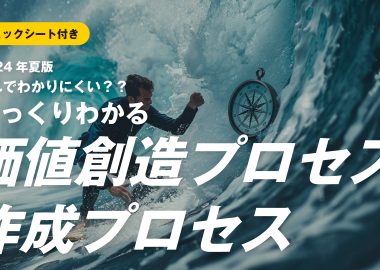

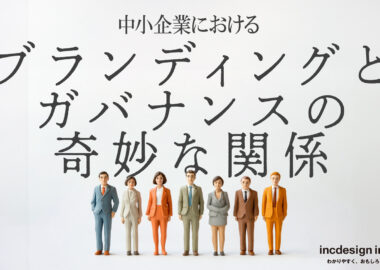
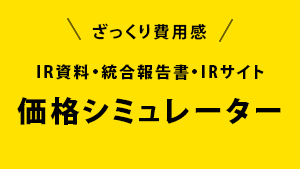



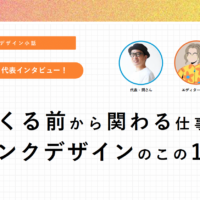
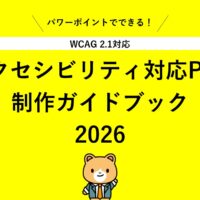
色々_むつき-200x200.jpg)